まずはお気軽にご相談ください
初回相談は無料・オンライン対応可
【無料】役立つ法務・労務コラムをお届け
ご検討・社内共有用にお使いいただけます

インターネットやSNSが生活の一部となった現代では、誰もが簡単に情報発信できるようになりました。写真や動画、音楽、文章をシェアすることは日常的な行為です。しかし、その便利さの裏側には、常に著作権や肖像権といった「知的財産権」に関する問題が潜んでいます。
「知らなかった」「悪意はなかった」では済まされないのが、知的財産権の侵害です。一度、法的トラブルに巻き込まれると、多大な時間と費用、そして精神的な負担を強いられることになります。
今回は、専門家である弁護士の視点から、著作権・肖像権の基本から、侵害した場合に科される罰則、そしてトラブルを未然に防ぐための注意点まで、皆様が知っておくべきポイントを徹底的に解説します。この記事が、皆様のインターネット上での活動をより安全で健全なものにする一助となれば幸いです。

吉野モア法律事務所 代表
京都大学法科大学院卒業 大阪弁護士会所属。
2022年に吉野モア法律事務所を開所し、主に中小企業のコンプライアンス問題や外国人労働者等の労災・労務問題、事業リスク・事業開発に伴う法的アドバイス等を実施。
直近は「トラブルが起こる前に備える」企業法務を目指し、組織づくりや次世代経営者育成なども手掛けている。
まずは、「著作権」と「肖像権」の違いを明確にしましょう。両者は人の「権利」を守るためのものですが、その対象は根本的に異なります。
著作権は、思想や感情を創作的に表現したもの、つまり著作物を保護する権利です。著作物には、以下のようなものが含まれます。
著作権は、著作物が創作された時点で自動的に発生します。特許権のように特許庁への登録といった特別な手続きは一切必要ありません。この「無方式主義」は著作権法の大きな特徴です。
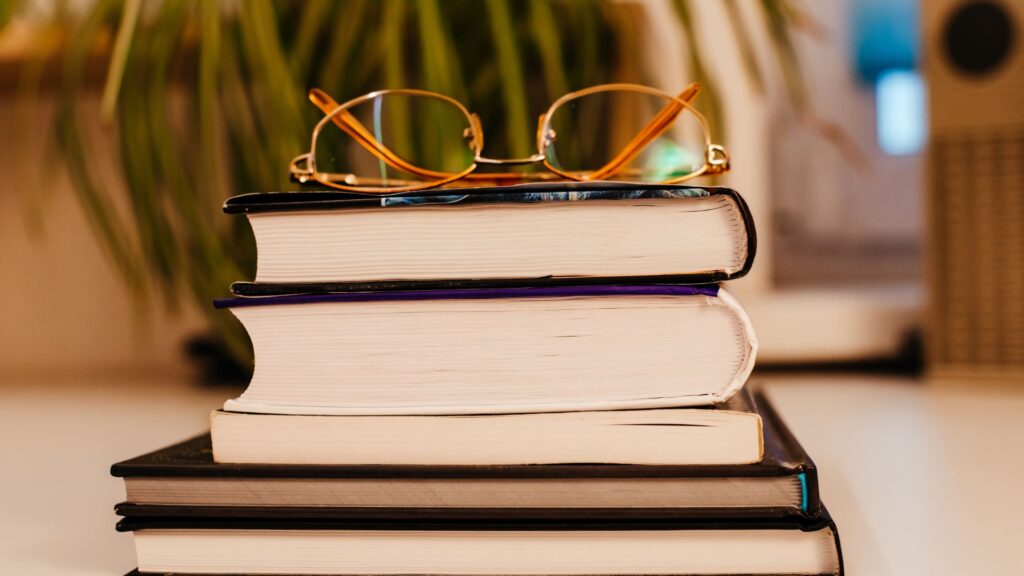
また、著作権は、著作者が持つ著作者人格権と著作財産権の二つに分けられます。
肖像権は、個人の顔や姿がみだりに撮影されたり、公開されたりしないように主張できる権利です。これは、プライバシー権の一部として考えられており、日本国憲法第13条で保障されている幸福追求権を根拠とする人格権の一種とされています。
肖像権は、判例によって認められてきた権利であり、法律に明確な条文があるわけではありません。しかし、他人の顔や姿を無断で撮影したり、インターネットに公開したりする行為が社会的に許容されないことは、多くの裁判例で示されています。
▼最新の判例や企業法務に関するお役立ち情報は、吉野モア法律事務所のメルマガもご利用ください。
また、肖像権と似た権利として、有名人やタレントなどが持つパブリシティ権があります。
この2つの権利は、肖像権がプライバシーを守るという意味で人格的利益を保護するものであるのに対し、パブリシティ権は有名人の肖像等が持つ財産的利益を保護するものであるという点で異なります。
著作権や肖像権を侵害した場合、どのような法的責任を問われるのでしょうか。その責任は、大きく民事上の責任と刑事上の責任に分けられます。
権利を侵害された側(被害者)は、加害者に対して民事上の責任を追及することができます。
著作権侵害は、刑事罰の対象となる可能性があります。著作権法には罰則規定が設けられており、著作権を侵害した者には、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、もしくはその両方が科される場合があります。さらに、法人による侵害の場合は3億円以下の罰金が課されることもあり、非常に重い罰則であることがお分かりいただけるでしょう。
肖像権侵害自体には刑事罰の規定はありませんが、無断で他人を撮影し、悪意をもって公開する行為は、名誉毀損罪(3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金)やプライバシー侵害として、別途法的な責任を問われる可能性があります。

「知らなかった」という言い訳が通用しない以上、日頃から知的財産権を侵害しないよう、細心の注意を払う必要があります。特に、著作権がどこから「侵害」とみなされるのかという境界線を知ることが重要です。
インターネット上の情報を安易に使わない
ブログやSNS、ウェブサイト上の画像、音楽、文章などは、全て誰かの著作物である可能性があります。「検索して出てきたから自由に使っていい」という考えは非常に危険です。利用したい場合は、必ず著作権者からの許可を得るか、著作権フリー(利用規約をしっかり確認)のものを使用しましょう。
人物が写った写真を公開する際は必ず許可を取る
友人と撮った記念写真や、街中で見かけた風景にたまたま人が写り込んでいる場合でも、SNSなどに公開する際は、写っている本人から許可を取りましょう。特に、不特定多数の人が閲覧できる場所では、予期せぬトラブルにつながるリスクが高まります。
引用のルールを遵守する
著作権法では、他人の著作物を正当な目的で利用する「引用」が認められています。しかし、このルールを正しく理解しておくことが著作権侵害を防ぐために重要です。どこからが適法な引用の範囲なのかをチェックしましょう。

著作権や肖像権の問題は、その内容の複雑さから、個人間や企業内で解決することが非常に難しいケースが少なくありません。
「この使い方は問題ないだろうか?」「もしかして権利を侵害しているかもしれない」と少しでも不安に感じた場合は、罰則や損害賠償のリスクを避けるためにも、放置せずに早めに専門家である弁護士にご相談ください。また、万が一トラブルに巻き込まれてしまった場合も、法的な根拠に基づいた適切なアドバイスとサポートを提供します。
ご自身の権利を守るため、そして他者の権利を尊重するためにも、知的財産権に関する正しい知識を持ち、健全なインターネット社会を築いていきましょう。何かご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
初回相談は無料・オンライン対応可
【無料】役立つ法務・労務コラムをお届け
ご検討・社内共有用にお使いいただけます