まずはお気軽にご相談ください
初回相談は無料・オンライン対応可
【無料】役立つ法務・労務コラムをお届け
ご検討・社内共有用にお使いいただけます

職場でハラスメントが発生したとき、企業にとって最も重要な対応のひとつが「迅速かつ正確な事実調査」です。調査の進め方を誤れば、被害者や加害者から「不公平だ」と反発を受けたり、企業の法的責任を問われる可能性もあります。
こうしたリスクを避け、公正な調査を行うためには、複数人で構成される「ハラスメント調査委員会」の設置が欠かせません。本記事では、ハラスメント調査委員会の設置方法から具体的なヒアリング手順、報告書のまとめ方まで、初心者でも理解できるように整理して解説します。

吉野モア法律事務所 代表
京都大学法科大学院卒業 大阪弁護士会所属。
2022年に吉野モア法律事務所を開所し、主に中小企業のコンプライアンス問題や外国人労働者等の労災・労務問題、事業リスク・事業開発に伴う法的アドバイス等を実施。
直近は「トラブルが起こる前に備える」企業法務を目指し、組織づくりや次世代経営者育成なども手掛けている。
従業員から「ハラスメントを受けたかもしれない」という相談があったとき、会社は「気のせいじゃないか」と放置することは許されません。なぜなら、会社には法律で定められた「調査義務」があり、これを怠ると大きなリスクを負うことになるからです。
そして、その調査を正しく行うために「ハラスメント調査委員会」というチームを組むことが非常に重要になります。

法律で定められた企業の「調査義務」とその重要性
2022年4月から、大企業だけでなく中小企業も含めたすべての会社で、パワーハラスメント防止措置が義務化されました(※1)。厚生労働省が定めた指針では、従業員からハラスメントの相談があった場合、会社は迅速かつ正確に事実関係を確認する義務を負うとされています。
もし、この調査を怠ったり、不適切な対応をしたりしたことにより被害者の心身の不調が悪化したり、退職に追い込まれたりした場合、会社は安全配慮義務違反として被害者から損害賠償を請求される可能性があります。
調査委員会を設置する最大のメリット
では、なぜ調査は人事担当者一人が行うのではなく、「調査委員会」というチームで行う必要があるのでしょうか。それは、調査の「公平性」と「中立性」を保つためです。
例えば、人事部のAさんが調査担当者になったとします。ハラスメントをしたとされるBさんは、Aさんと同期入社でとても仲が良い同僚で、被害を訴えたCさんは中途入社したばかりで、Aさんとはあまり接点がありません。この状況でAさん一人が調査すると、無意識にBさんを擁護し、Cさんの話を軽視する可能性を否定できません。
こうした事態を避けるため、人事担当者だけでなく、法務担当者や、当事者とは直接利害関係のない他部署の管理職などを加えた複数名の「調査委員会」を設置するのです。複数の視点で事実確認を行うことで、個人の感情や思い込みに左右されず、客観的な判断がしやすくなります。
ここからは、ハラスメント調査委員会を設置する具体的な方法について解説します。
調査委員会を設置する最大の目的は、調査の「公平性」を担保することです。そのため、メンバー選定では以下のような点を考慮することが重要です。
【基本構成】
調査委員会は、人事・労務や法務の担当者に加え、当事者と直接の利害関係がない他部署の管理職などを含めた、3〜5名程度の複数名で構成するのが望ましいとされています。多様な立場のメンバーで構成することで、多角的な視点から事実を検討でき、より客観的な判断につながります。
【相談内容に応じたメンバーの多様性】
ハラスメントは、セクシュアルハラスメントなどと複合的に生じることも想定されます。そのため、相談内容によっては、委員会メンバーの性別等に偏りが出ないよう配慮することも重要です。被害者が安心して話せる環境を整えるという観点からも、メンバー構成の多様性は不可欠です。
ハラスメント調査は社内で行うのが基本ですが、いつもそれが最善とは限りません。役員が関わっているなど社内だけでは公平な判断が難しいケースや、事案がとても重大な場合には、必要に応じて外部の専門家である弁護士と連携することが有効です。

弁護士は、多くのトラブルを解決してきた経験から、紛争の原因や対応策、そして問題が二度と起きないようにする予防策についても詳しい知識を持って持っています。加えて、法的リスクの判断や将来的な訴訟を見据えた証拠収集、調査結果を踏まえた懲戒処分の適法性の検証など、企業側の法的な防御という観点から社内調査では得られない客観性と専門性を有しています。
相談できる弁護士がいない中小企業の場合でも、「ひまわりほっとダイヤル」のような相談窓口が設置されていますので利用してみることをおすすめします。
▼ 弊所でもご相談を承っておりますので、お気軽にお問合せください。
ハラスメント調査に関するご相談はこちら
ハラスメントの相談があった場合、企業は迅速かつ適切な対応をとることが求められます。対応が遅れたり不適切だったりすると、企業が法的責任を問われるリスクが高まります。ここからは、誰もが納得できる公正な調査を進めるための具体的なステップを解説します。
ハラスメントの調査を進めるにあたり、関係者全員を守るために、会社が必ず守らなければならない2つの重要なルールがあります。
1. プライバシーの保護
会社は、相談者や行為者など、調査に関わった人たちのプライバシーを厳重に保護する義務があります。特に、性的指向・性自認や病歴、不妊治療といった他人に知られたくない機微な個人情報が、社内で噂になったり漏れたりしないよう、細心の注意を払わなければなりません。そのために、あらかじめマニュアルを整備したり、相談窓口の担当者に研修を行ったりするなどの対策が必要です。
※相談窓口の設置方法や対応の注意点については、こちらの記事(機能するハラスメント相談窓口の作り方)もご覧ください。
2. 不利益な取り扱いの禁止
「ハラスメントの相談をした」「調査に協力した」といった理由で、その従業員を解雇したり、嫌がらせをしたりするなどの不利益な扱いをすることは、法律で固く禁じられています。会社は「相談しても絶対に不利益なことはしない」というルールを就業規則などで明確に定め、全従業員に周知・啓発する義務があります。
▼ ハラスメント調査や企業法務に関するお役立ち情報は、吉野モア法律事務所のメルマガもご利用ください。
メルマガ登録はこちら
関係者からのヒアリングや証拠収集が終わったら、集めた情報を基にハラスメントが実際にあったのかを判断する「事実認定」を行います。
事実認定は、調査委員会が客観的な証拠に基づいて行います。当事者双方の話が食い違う場合は、どちらの主張がメールなどの客観的な資料と合っているか、話に矛盾がないかなどを総合的に考慮して慎重に判断します。
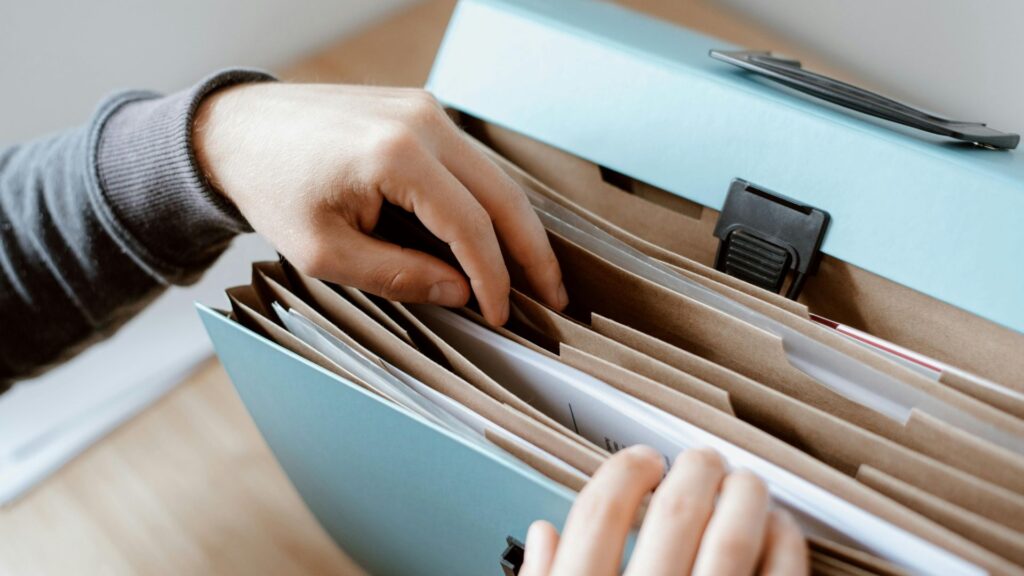
事実調査が完了し、調査委員会が報告書をまとめたら、それで終わりではありません。その客観的な報告書は、会社が次の具体的なアクションを起こすための重要な根拠となります。ハラスメントの事実が確認できた場合、企業は速やかに以下の措置を講じる必要があります。
• 被害者への配慮措置
まず最優先されるべきは、被害を受けた従業員への配慮です。具体的には、被害者と加害者を物理的に引き離すための配置転換や、加害者からの謝罪、メンタルヘルス不調への相談対応といった措置を、事案の内容や状況に応じて適正に行います。
▶ 関連記事:従業員がメンタルヘルス不調になった際の管理職の責任と対応方法はこちら
• 加害者への処分
加害者に対しては、就業規則や服務規律に定められた懲戒規定に基づき、厳正な処分を下します。処分の内容には、注意指導、減給、降格、解雇などがあり、行為の悪質性や被害の程度に応じて適切なものが選択されます。
▶ 関連記事:服務規律・解雇ルールの見直しポイントはこちら
ハラスメントの事実調査は、法律で定められた企業の義務です。対応を誤ると、損害賠償責任だけでなく、生産性の低下や信用の失墜といった深刻な経営リスクに繋がります。
いざという時に迅速かつ公正に対応できるよう、調査委員会や調査マニュアルを事前に整備しておくことが何より重要です。もし対応に迷う場合は、一人で抱え込まず、まずは弁護士などに相談してみることを推奨します。
吉野モア法律事務所でも、ハラスメント発生時の対応やハラスメント調査委員会の設置に関するご相談も受け付けています。お困りの際は、お気軽にご相談ください。
※1: 厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産等、育児・介護休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)」
初回相談は無料・オンライン対応可
【無料】役立つ法務・労務コラムをお届け
ご検討・社内共有用にお使いいただけます